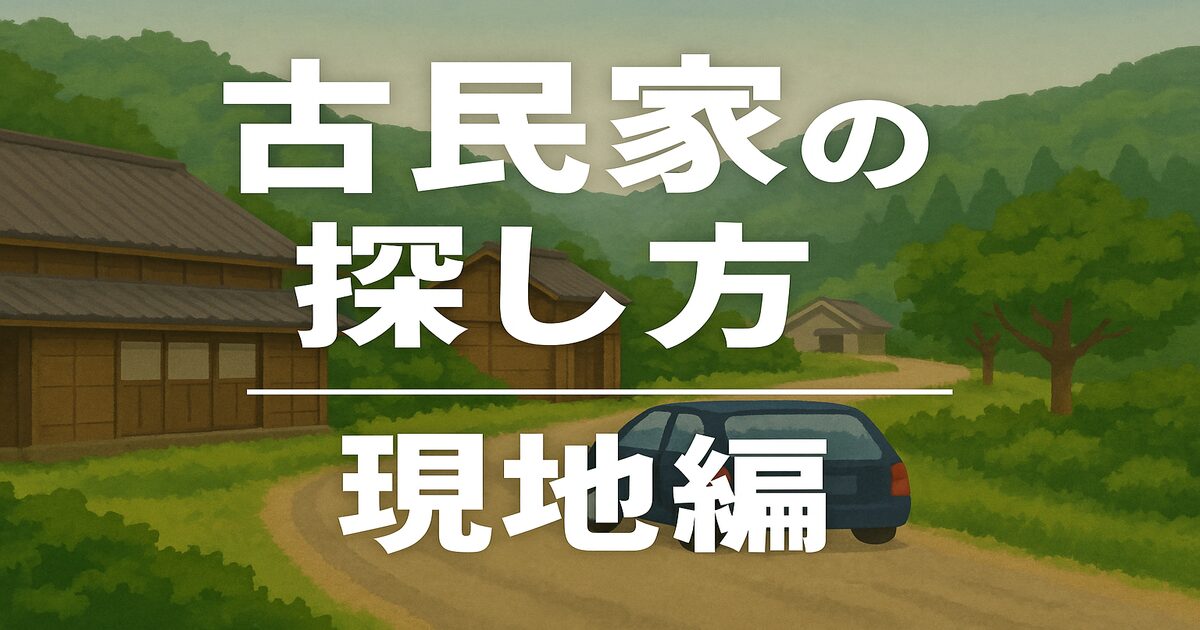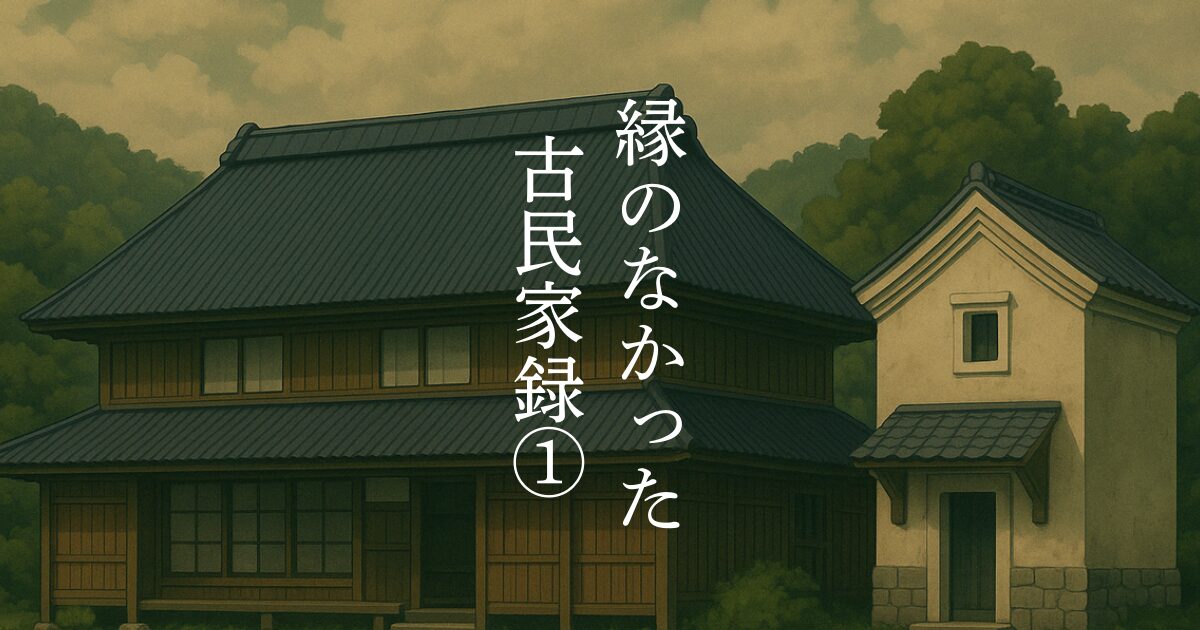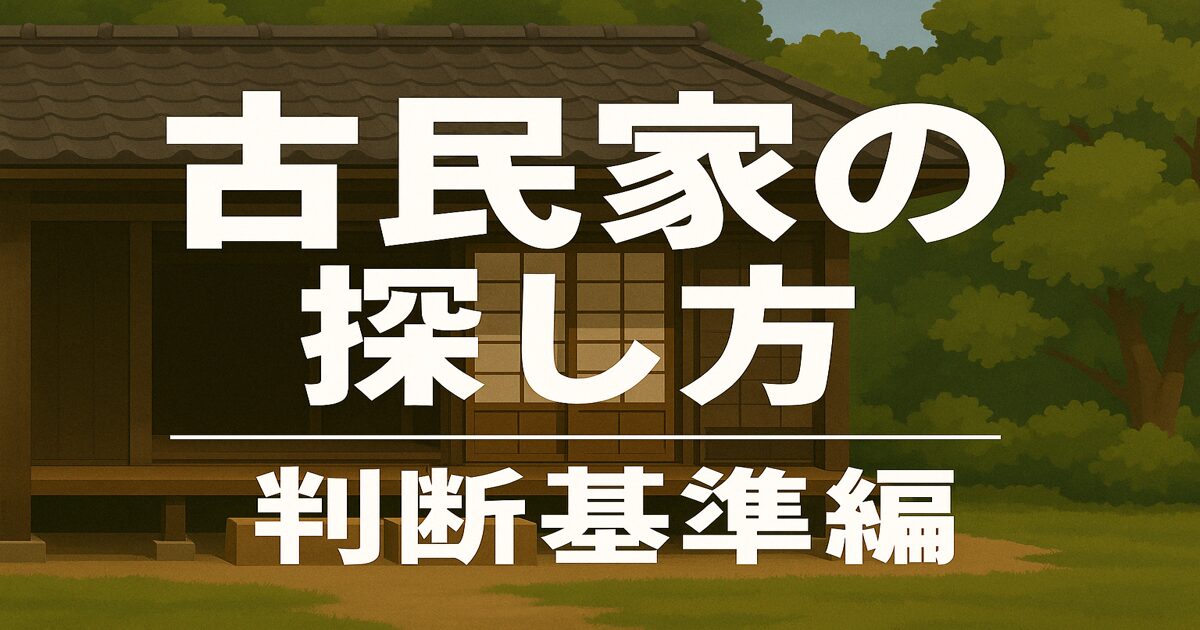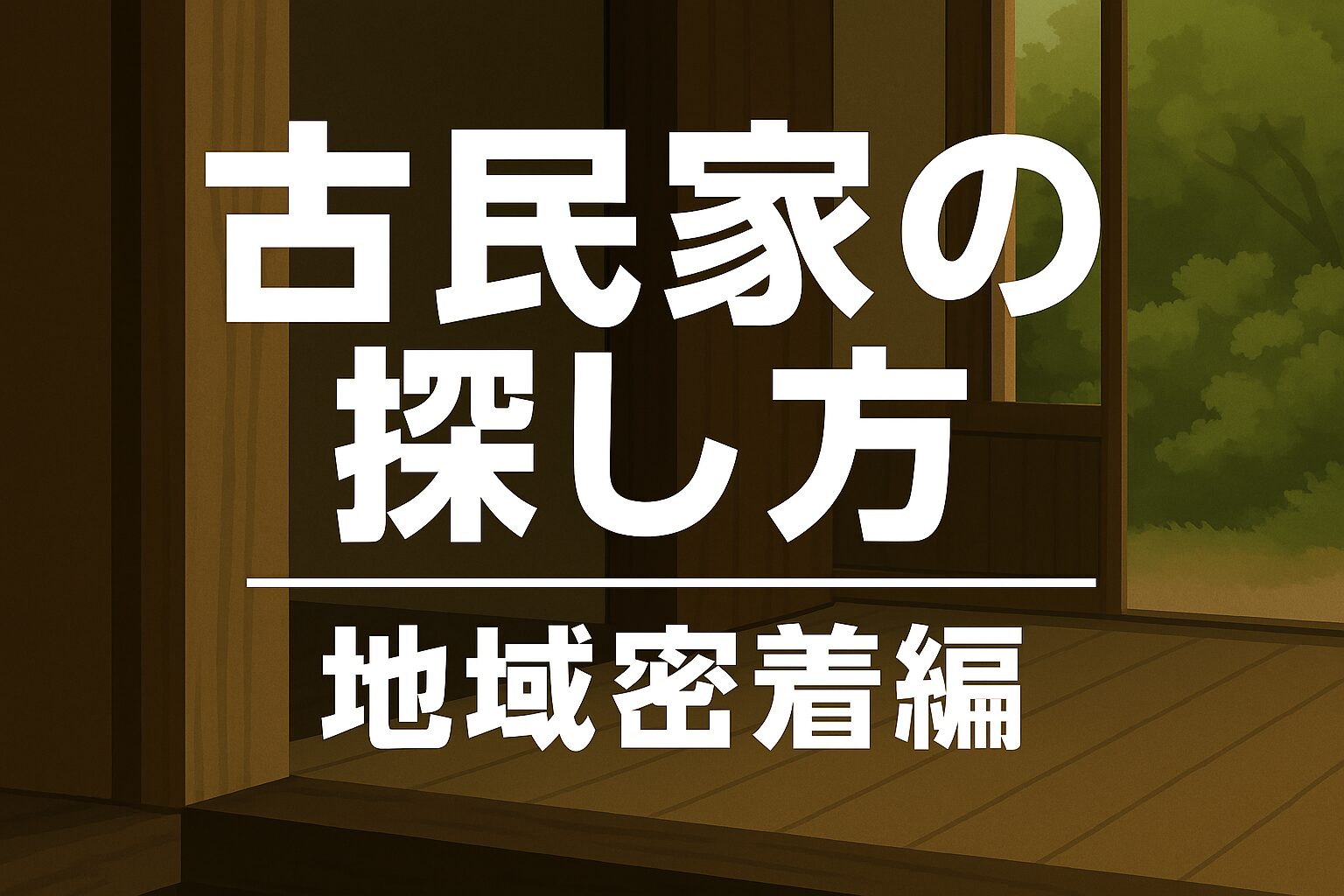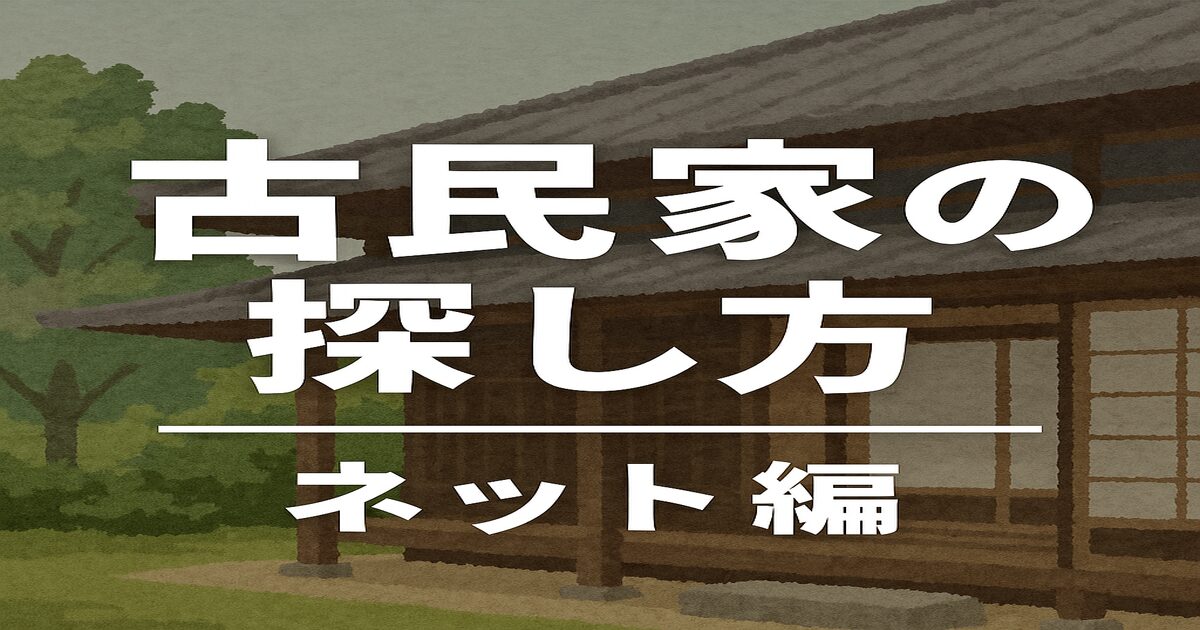私が古民家を探していた際、まずは普通にネットで検索を行いました。
SUUMO、アットホーム、ホームズなどの定番サイトは一通り確認しましたが、正直なところ古民家がほとんど出てこない印象を受けました。
「古民家」という紹介文があっても、実際には新しめの「古民家風リノベ済み」物件が多く、築年数で並べ替えても思っていたような本物の古民家はほとんど見当たりませんでした。
古民家の探し方【実践編】
そこで私が行ったのは、Googleマップを活用して古民家らしい家を探し、気になる物件をお気に入り登録しておく方法です。
その後、現地に足を運んで空き家かどうかの様子を確認し、地域密着型の地元不動産会社に所有者の情報を調べてもらうという流れを取りました。多少荒技ではあるけど。
注意点として、ここでいう不動産会社っていうのはいわゆる大手(例えば積水ハウスとか)ではなく、地域密着の地元の不動産のこと。後述しますが、そういったところを見つけられると楽だし役に立ちます。そういったところの見つけ方(というか私が見つけたやり方)も今後紹介していければと思います。
古民家再生協会所属の工務店に同行を依頼した経緯
いきなり話飛びますが、物件を探している中で、「良さそうだけど構造的に大丈夫だろうか?」と不安を感じることもありました。最終的に、見に行った物件の約7割は私一人で見学しましたが、素人目線だけでは判断が難しい場面も多かったです。
そのタイミングで、自分は古民家再生協会に所属している地元の工務店に相談し、物件を一緒に見てもらうことにしました。
この工務店は、古民家ポータルサイト「クロニカ」の大原さんに紹介していただき、直接連絡を取り、会ってお話を進めていきました。実際に話してみると、古民家への思い入れが強く、私の「構造はできるだけ活かしたい」「古民家の空気感を残したい」という考えにも共感してくださり、安心感を持てました。
また、実際に自分たちで古民家を手がけていたり、石場建ての構造にも触れていたりして、技術的にも信頼できる印象を持ちました。
依頼したのは物件の紹介ではなく、あくまで私がネットで見つけた物件を一緒に見て、リフォームを前提に現実的に可能かどうかを判断してもらうことでした。さらに、「価格は妥当か」「どの程度のリフォーム費用が必要か」といった点も総合的に見ていただきました。
同行していただいた際には、具体的に「この柱は補修で済みそうです」「この梁の太さなら十分使えますね」といった専門的なコメントをいただき、私の判断に大きなズレがなかったことを確認できて安心しました。最終的には、そのままリフォームもすべてその工務店にお願いすることになりました。
「同行=リフォーム契約前提」ではありませんが、私の場合は石場建てを残したいという強いこだわりと、古民家再生協会の看板に対する信頼感があり、最初から「この工務店にお願いするかもしれない」という気持ちもありました。
工務店同行のメリットとデメリット
【メリット】
- プロの目線でその場で建物の状態を診断してもらえる
- 傾きや柱の傷み、屋根や床下の状況など、自分では気づけないポイントを教えてもらえる
- 予算感のズレを早めに把握できる
- 見積もり前に「この家を直すとどれくらいかかりそうか」という肌感を知ることができる
- 「この家をどう活かすか?」といった相談ができる
- ただの劣化チェックだけでなく、「どこを残すか」「どう活かすか」といった専門的なアドバイスが得られる
【デメリット】
- 一度同行してもらうと他の工務店に切り替えづらくなる可能性がある
- 「ここまでやってもらったのに別の工務店にするのは申し訳ない」と感じやすい
- 気軽に見学できなくなる空気感が出てしまう
- 同行=リフォーム前提の空気になるため構えが必要になる
- 購入の気持ちが固まっていない方にはプレッシャーになるかもしれない
私の場合は良い出会いとなりましたが、他の方が同じようにうまくいくとは限りません。
今振り返ると、同行を依頼するタイミングや自分の考えの整理をもう少し行ってからでも良かったのかもしれないと感じています。
同行をお願いする際は、「自分の希望や優先順位がある程度固まっているか」「本気で相談しても良い相手かどうか」を見極めてから動くことをおすすめします。
「探しています」と発信する重要性
自分で探すだけでなく、職場や知り合いにも「古民家を探しています」と積極的に伝えていました。
田舎で情報を得るには、こちらから動いて発信することが何よりも重要です。何気ない会話の中で「〇〇の家が空いているらしいよ」といった情報を得られることもあります。
ネットに載っていない物件を見つけるには、こうした草の根的なアプローチが意外と効きます。
ただし、知り合い経由での情報にはメリットとデメリットがあります。
古民家好きであれば一定の基準がありますが、そうでない人にとっては「古くて大きい家=古民家」というイメージが強く、親切心で教えてもらった物件が実際には「古民家風の新しい家」だったというケースが多々ありました。
古民家の玉数自体が少ないので、私自身紹介されたところは全て見る位の勢いでいました。実際数を見ることによって、自分自身の古民家に対する目も養われるため、最初のうちは数を見る事は大事だと思います。
貴重な分空振りが多くなったとしても労力を使って探していくべきだと思います。田舎の場合は本当にどこで人と人がつながっているかわからないので、知り合いの知り合いから紹介されるということも時々ですがありました。
田舎では人と人のつながりが予想外のところにあることも多く、知り合いの知り合いから紹介されることも時々ありました。
「見えない空き家」には理由がある
古民家には古民家特有の売りたくてもネットに出せない事情が存在します。どちらかというと古民家というより田舎特融と言い換えたほうが正しいかもしれません。
古民家を探してると、誰も住んでるようには見えないけど、やたらきれいにされてる家っていうのを、おそらくどこかのタイミングで見つけることがあると思います。
車も止まってない、人の手入りもない。でも、庭の草は狩られている。その背景には、売主によるポジティブな理由とネガティブな理由が存在します。
ポジティブな理由としては、単純に思い入れが強い家。先祖代々の家だから、売りたくない。もしくは本家として残すべき家である。だから売れないというより売りに出さない。
一方で、ネガティブな理由としては田舎特有の人間関係の空気感があります。
親族や近所から「あそこ売ったらしいよ」と言われるのを気まずく思い、表立って売りに出せないケースも多いです。こうした田舎独特の空気感は、古民家暮らしをする上で避けて通れないものです。でも田舎って、そういう“外から見えない関係性”がすごく強い。
そういった田舎特有の空気感は、古民家に住む上では切っても切れないものになってくるでしょう。なぜなら、古民家が残っている地域や土地と言うのは大抵の場合、田舎だからです。
仮に都会に古民家のような広い土地を持った場所があったら、興味ない人にとっては、古民家はただの古くてぼろい家なので、速攻取り壊されて分譲地にされるのがオチです
土地や家だけじゃなくて、人との距離感や空気も含めてその土地で暮らしていく、そういったところも含めて受け入れていくということが必要になってくるでしょう。
古民家の持ち主は「うちの家なんて」と思っていることも多い
築100年超の立派な古民家でも、持ち主にとっては“ただの実家”。
価値のある家なのに、「こんなボロい家、誰が欲しがるんだろう?」って感覚のまま、「手放せるなら手放してもいいなぁ」と思っていてもずっと誰にも相談せずにいるパターンも少なくない。
特に昔の人にとっては、無垢材の梁や太い柱なんて「当たり前」の存在。それが“価値のあるもの”だなんて、あまり思ってないこともある。だから、そもそも売れるとも思ってないし、売るという選択肢自体がまだ現実味を帯びてない。
結果として、行動に移していないだけというケースもかなりある。
そういった家については交渉次第で売ってくれる可能性はあると思いますが、やはり古民家の持ち主も高齢になっていることが多く、その持ち主の子供は他県に住んでいるというパターンも少なくありません。結果として売る気はあるけれども、行動に移せないということもあるため、その辺は不動産会社とも連携しながらうまく進めていく必要があります。
出会いはタイミングと信頼がカギ
私が印象に残っている物件のひとつに、「今は誰も住んでいないが、大事な家なので売れません」と断られた古民家があります。見た目は立派で、草も刈られており管理が行き届いており、売りに出たら即購入したいレベルの古民家。ちなみに、その家を見つけた方法もGoogleマップです。
でも、不動産会社経由で確認してもらったところ、「ここは昔からの本家なので、申し訳ないですが売れません」ときっぱり断られました。
その人にとって、その家は「モノ」じゃなくて「家族の歴史そのもの」であり、売ることで何かが断ち切られるような気がしていて、だから簡単には手放せない。一方で、「いつかは手放さないといけない」とも思っていたようで、「今は売る気はない」とも言われていました。
その方と話せる機会を持たせていただきましたが自身の年齢のこともあるし、管理し続けるのも限界がある。
理想は、息子や娘が引き継いでくれることだけど、今の若い世代は新築志向が強いし、広すぎる・寒い・手間がかかる等々古民家を敬遠する人も多い。だからこそ、古民家に思い入れのある方であればあるほど手放すなら“ちゃんとわかってくれる人に譲りたい”という想いがある。
そういった場合、値段の問題ではなく、どれだけ売る相手が古民家に対して本気であるかを見ていることが多いです。
家の背景や想いまで受け取ってくれるような相手じゃないと、紹介すらされない。でも、こういった物件と出会えるかどうかは、本当にタイミング次第なところもある。
たまたま情報が回ってきたときに動けたか、話を聞いてもらえる関係性があったか、買える準備はできていたか…
自分の努力だけではどうにもならない部分も確実にある一方で、そういった古民家に出会えた事は非常に幸運であり、チャンスでもあります。もちろん売ってくれる可能性は低いですが、そういった古民家は大事にされている分、定期的に管理もされており、状態として非常に良いことが多いです。
結局の所、どんなに立派な梁や大黒柱を持っていたとしても、所詮古民家は木と土なので、手入れしなければすぐに自然に帰ります。つまり朽ちていきます。
だからこそ日々の手入れが必要であり、そういった古民家を見つけられたことは非常に幸運です。
同時に管理をして守ってきた持ち主に対してもリスペクトを持つべきだと思います。
古民家探しに必要なのは「本気度」
古民家探しって、物件検索というより、情報と人との出会いに近い。
ネットに出てこない家、行動しなければ見えてこない情報、そして、信頼されないと話が進まない空気感。
そういう要素が入り混じってる。
もちろん、売主が早く手放したがっているから、スムーズに話が進むこともある。
でも、そういう古民家はたいてい手入れがされておらず、状態が悪いことも多かった。
だからこそ、探す側も“どこで、誰と、どうつながるか”が大事になってくる。
そんな「人づてで出てくる情報」にどうアプローチしていったのか──
自分が実際に動いた中でも特に重要だった、地元密着の不動産会社や工務店との関係づくりについて書いていきます。
長いな。しゃーない。