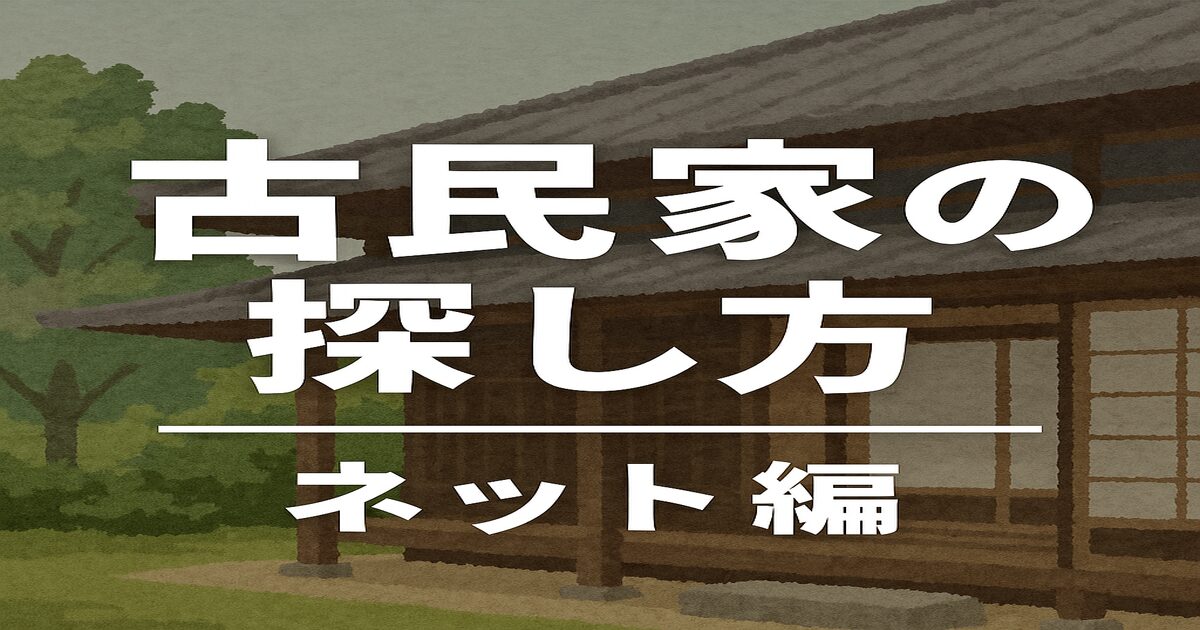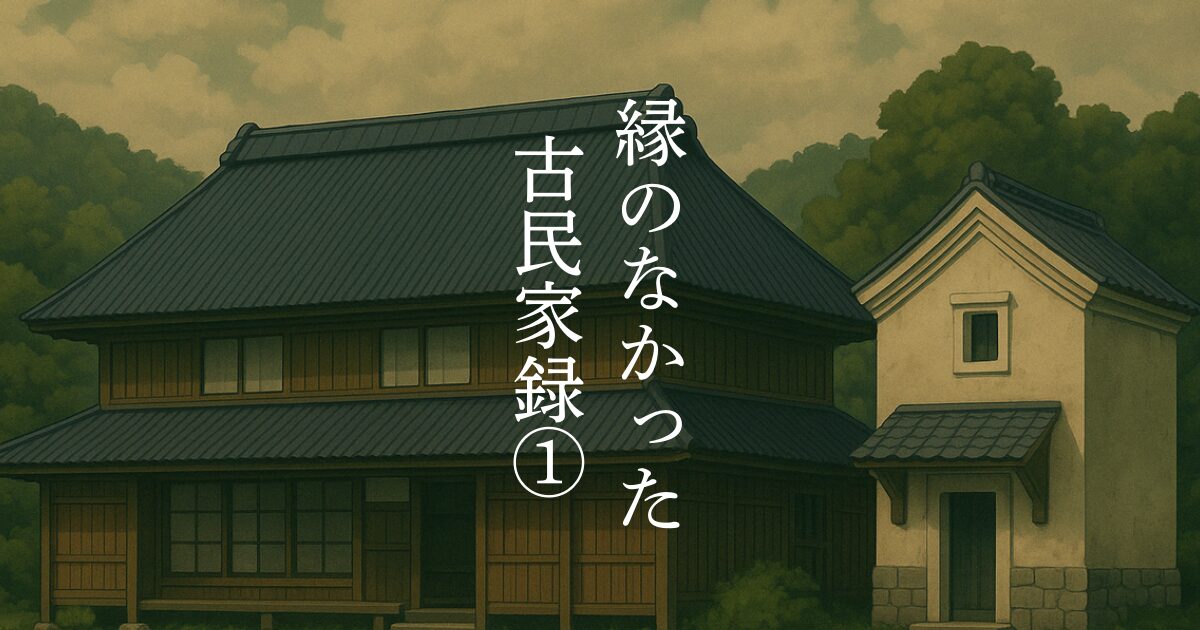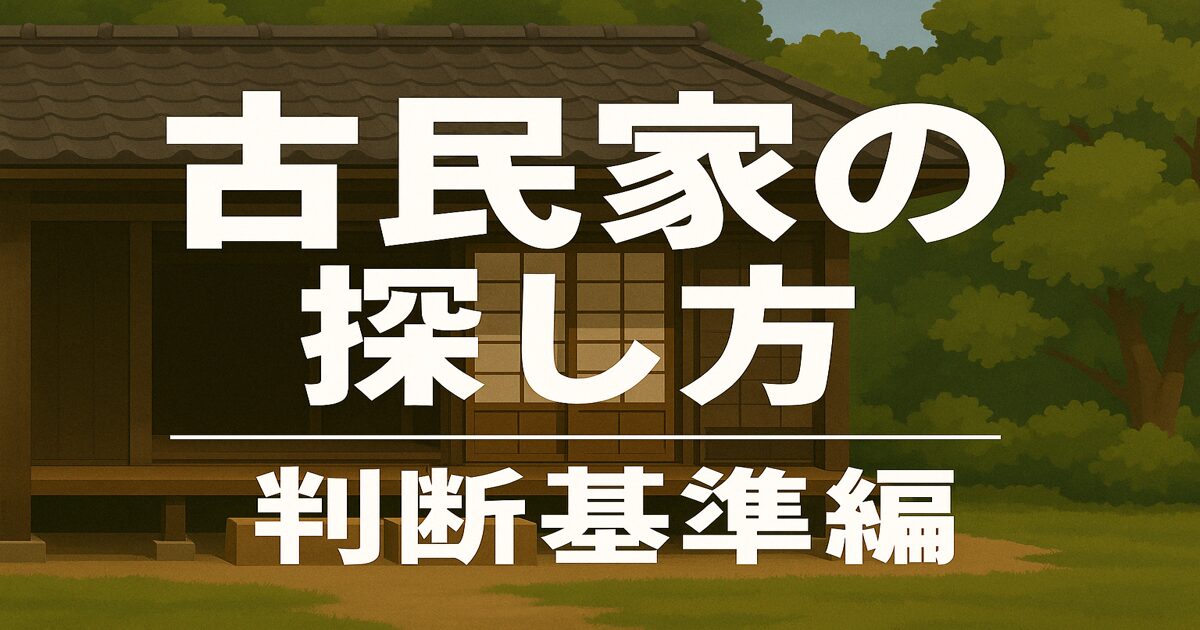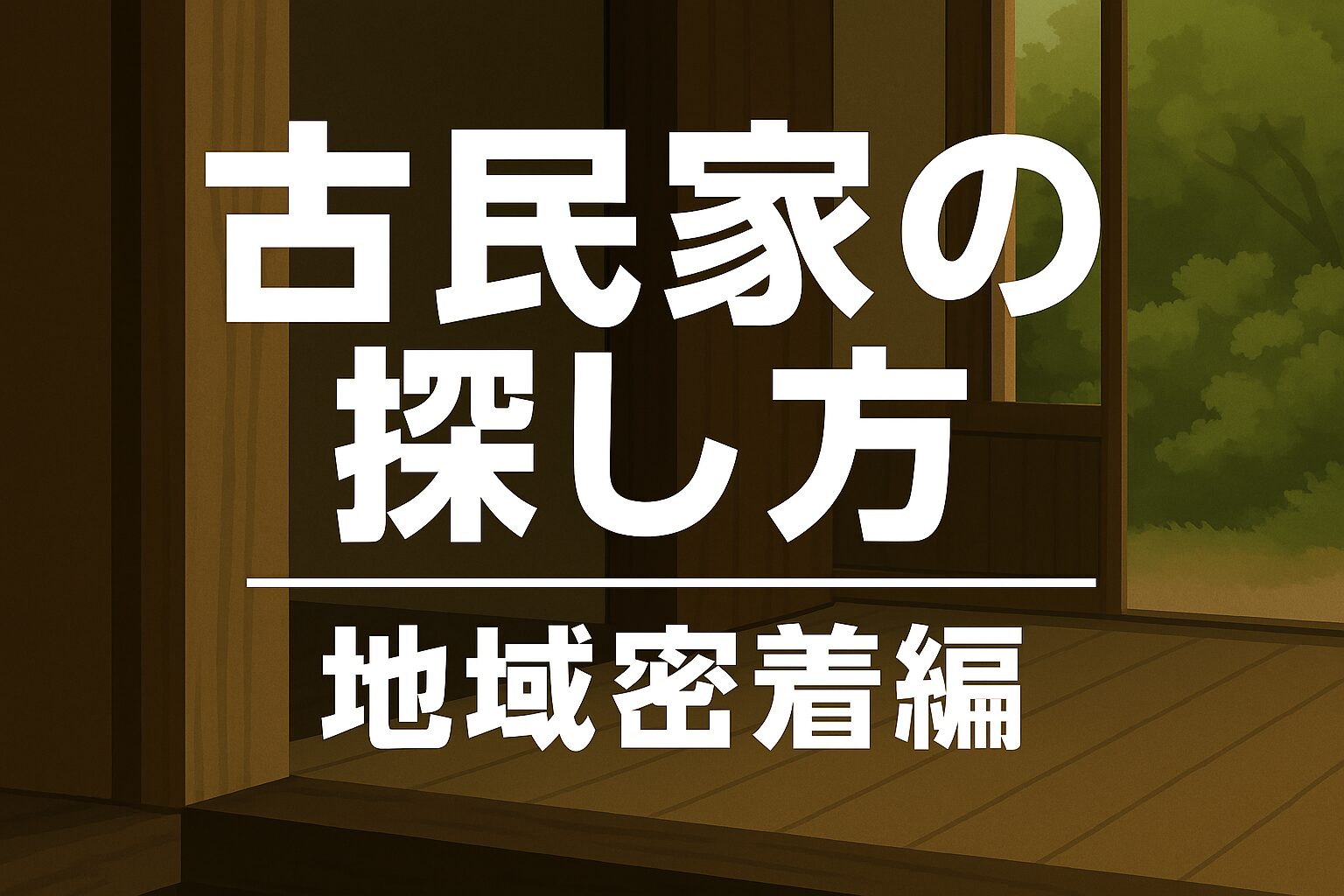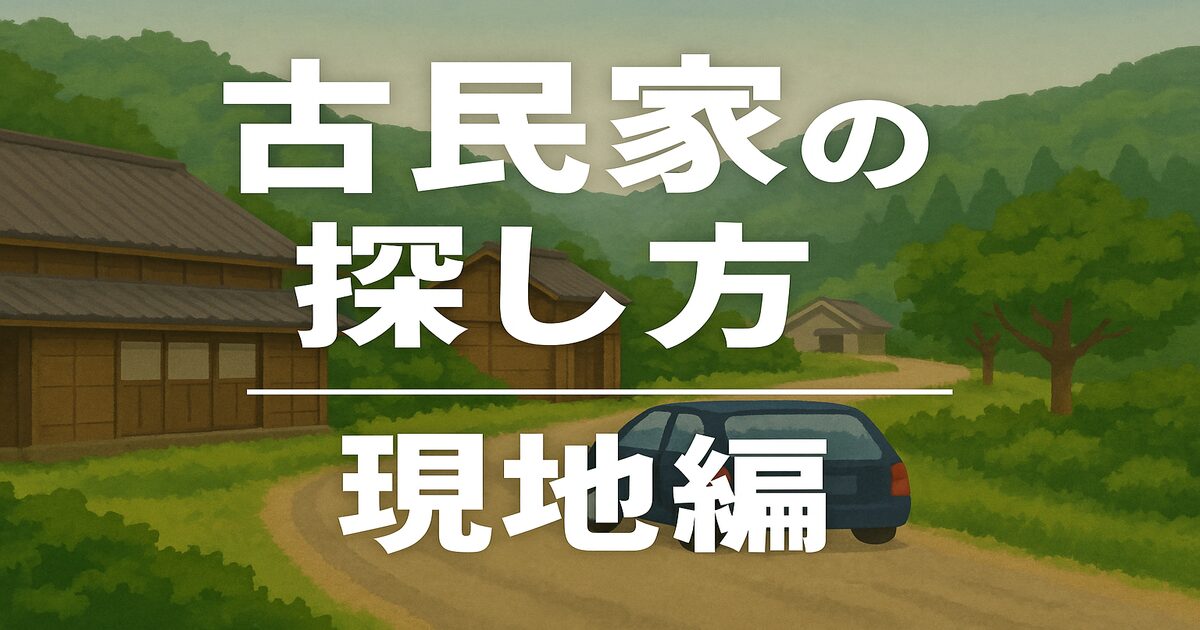古民家って、理屈じゃなくて「なんかいいな」と思うところがある。
うまく言葉にできないけど、あの雰囲気とか、佇まいとか、そういうものに惹かれてしまいます。
他人のリノベブログを時系列で読むのって、けっこう楽しいよね。どんなふうに物件を見つけて、どこで悩んで、どう暮らしてるのか──気づいたら読み込んでたりする。
「いいな」と思ったところから、なんとなく動き出して、気づいたら結局購入して住宅ローン組んでいるところまで来てしまった──私の場合はそんな話を書いていくブログです。
もちろん、すぐにリノベーションの話に入れるわけじゃないけど、今回からはその過程をひとつずつ振り返っていく感じになると思います。
流し読みでもいいので、気が向いたときにでもどうぞ。
ちなみに、最近のブログの流行として、最初に結論を書けって言われる。これはGoogle的な推奨だったりショート動画が流行っている昨今では当然のことなんですが、わたくしあえてそういったことは致しません。
古民家っていうのはそういう効率や上手なやり方っていうのとは真逆だと思うんですよ。
だからこそ、「最初に結論」「箇条書きで表現」みたいなことはあまり意識せず書きたいと思います。
古民家探しはネットから
最初はただ古民家を眺めてただけ
最初はSUUMOやアットホームみたいな不動産サイトで、「築年数の古い順」で検索しては、気になる家を眺めているだけ。
この頃はまだ引っ越し前だったので、実際に見に行けるわけでもなかったから、写真を見ながら「こういう家いいな」だったり、「これはネットに載せて売れると思ってるのか?」とツッコんだり。
ほとんど“眺めるだけ”の楽しみ方に近かった気がします。
それでも、気になる物件はとりあえずブックマークして、場合によっては問い合わせて。
実際の購入までのリアルなイメージは湧いてなかったけど、それでも「古民家って、いいな」って思う気持ちは確実に強くなっていったし、自分の中での古民家像みたいなものはこの時に出来上がっていった気がします。
自分なりの探し方ができるまで
古民家って、見た目がいいだけじゃなくて、構造そのものも独特。
土壁とか真壁とか免震とか、最初は聞いたこともない言葉が出てきて戸惑ったけど、調べれば調べるほど「昔の人って、すごかったんだな」と思わされることばかり。前の記事でも語りましたが私は「伝統」や「引き継がれた」 みたいな言葉に弱いためまぁどんどん古民家にのめり込みます。
断熱のこと、虫との付き合い方、暖の取り方。
不便そうに見えるけど、それを楽しんでいる人たちの話を読んでいるうちに、「やっぱ古民家だなぁ」という気持ちが自然と強くなっていってましたね。
使ったサイトと、検索のちょっとした工夫
使っていたサイトは、SUUMO、ホームズ、アットホームの3つが中心です。
なんだかんだで不動産サイトを使って探すのが一番簡単ではある。中でも肌感として、アットホームは古民家っぽい物件が一番多く出ていた印象があります。
そのほかにも当然Google検索はするわけで。キーワードは「古民家」「和風建築」「平屋」「田舎暮らし」などを使い分けていたけど、実際はキーワードだけじゃ本物にたどり着けないことも多かった。
“古民家風”の昭和住宅だったり、古民家って呼んでるけど実は築50年くらいだったり。逆に古民家と呼ばれてないけど本物っぽい家があったり。
だから、建築年、梁の写り込み、基礎、間取り、敷地面積なんかを見ながら、「これはもしかして…」という勘を働かせる作業をずっとやっていました。ちなみに、Googleマップを使ってストリートビューや航空写真から気になる家を探すこともありました。
古民家に対する感性が鋭くなってくると、地図上でもなんとなくわかるようになるので、古民家っぽい家をお気に入りにして、あとから実際に見に行く、という使い方。
これはネットと現地の中間のような探し方だけど、探し方の一つとしてあります。あまり推奨はしないけど。
土地の広さ、家の広さもフィルターになる
自分の場合、古民家を探す上で「子どもが走り回れる庭」は絶対に外せない条件でした。だから検索条件に、敷地面積○㎡以上、といった設定を入れていた。まぁ大体の古民家には庭というか公園というか森みたいなやつまでついてくることがあるので心配ないのですが(?)
意外とこれがよく効いて、広い土地がついてる=古民家率が高い、みたいな傾向もあった。
物件数が多すぎて困る人には、面積でフィルタリングするのはおすすめだと思います。私はざっくりですけど土地面積の下限を300もしくは400にしてました。
築年数から“らしさ”を見極める
古民家を探していたとき、自分がよく使っていたフィルターのひとつが「築年数」。
特に目安にしていたのは1950年以前の建物かどうかだった。というのも、1950年に建築基準法が制定されて、それ以降は建物の構造や安全性に関するルールが細かく整備されていった。とはいえ、その時点で基礎が義務化されたわけではなく、木造住宅の基礎構造について明確な規定が入ったのは1971年の改正から。
でも、実際の物件を見ていると、やっぱり1950年以前の建物のほうが石場建てや伝統的な構法を使っている割合が高い。見た目では判断しづらいときもあるので、築年数を**“古民家らしさ”を見極めるための目安**として活用していた。
古民家が「土地」として出ていることもある
不動産サイトには「家」と「土地」のカテゴリがあって、実は古民家って「土地」枠で出てるケースも少なくない。というのも、古民家は建築年が古すぎて、不動産的な価値がゼロとされがち。
- 太くて長い梁が噛み合っている
- 今の家の2倍はあるくらいの大黒柱がある
- みんな大好き広い公園がついてくる
- 立派な手刻みの欄間や木組みがある
こんな家も築年数が古いだけで価値は0。
「ほんとにこれでいいんか?」とは思うけど、結果としてかなり安く手に入る現状はあるのでなんとも複雑な気持ち。
結果的に、「家付き土地」として、建物はおまけ扱いで売られてることもある。自分が買った家もまさにそれで、土地情報として出ていた物件。建物のことは一切ノータッチ、「現状渡しです」のスタンスだった。
だから検索するときは、「土地」カテゴリを見て、その中で“建物あり”みたいなチェックを入れて探すのがポイントになる。
ネット見ろ。足を使うのはそれからだ
ネットに出てくる物件は限られてるけど、それでも最初の入口としては十分だと思う。
むしろ、ここでいろんな物件を見て、自分の中の「好み」や「基準」を言語化したり自分の中に落とし込んでいくことが大事。この作業ができていると、実際に現地で見たときの判断も早くなる。ただ、やっぱり本物の古民家が少なくなっているのは事実。本当に欲しい古民家に出会うには、ネットの外側にも踏み込んでいく必要がある。
てことで次回は現地編です。
結局結論は?
「古民家はどうやって探す【ネット編】」とカッコつけてタイトルつけましたが、結局何が言いたかったんだってなってしまった。
とりあえず簡潔に言うなら
- アットホーム見る
- 家カテゴリーだけじゃなく土地の方も見る
- 空き家バンク見る(別記事)
- 恐れず問い合わせる
- いろんなサイト見る
- クロニカ
- 古民家住まいる
- 古民家Bank
- 日本民家再生協会
- みんなの0円物件
とにかく数見るの大事。