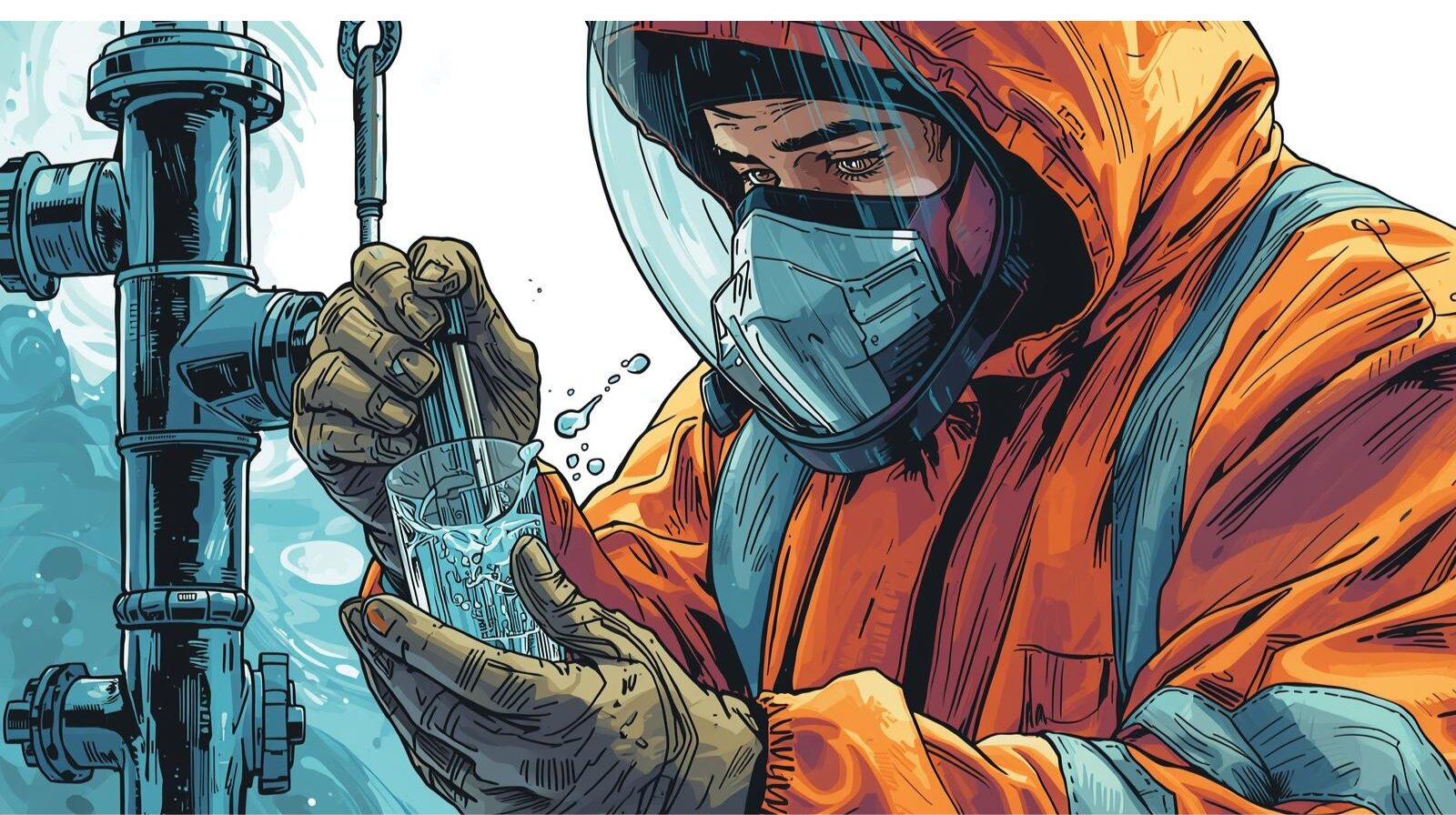私が夢見た、水と土の匂いがする暮らし
古民家での暮らしを思い描くとき、そこには決まって縁側と庭の風景があった。夏の日差しが照りつける午後、子供たちが庭で泥だらけになって遊んでいる。その傍らには、勢いよく水を噴き出すホース。水道のメーターを気にすることなく、心ゆくまで水と戯れることができる暮らし。それは、現代の都市生活では得難い、ささやかで、しかし本質的な豊かさの象徴のはずだった。
我が家の庭にも、その夢を叶えてくれるはずの主役がいた。古くから水を湛えてきた、大きな井戸である。だが現実は、私のささやかな理想にいつも少しだけ厳しい。その主役は、肝心のポンプが壊れて久しく、ただの大きな穴として鎮座しているだけだった。
庭の整備が掘り起こした、新たな希望と課題
先日、鬱蒼としていた庭の景観を改善すべく、専門の業者に清掃を依頼した。大金出して、人力ではどうしようもなかった木や草や木や木や池等不要な物が取り払われ、我が家の庭は設計図通りの姿を取り戻しつつあった。その作業報告の際、業者の担当者が少し困惑したような顔で私を離れの裏へと案内した。
そこに現れたのは、苔むした小さなコンクリートの塊だった。草木に隠れて、これまで誰もその存在に気づかなかった、第二の井戸である。
既存の大きな井戸は、その心臓部であるポンプの交換に見積もりを取ったところ、十数万円という、私の財布には少々手厳しい数字が提示されていた。水道代という継続的な支出と、高額な初期投資。その天秤の上で私の心は揺れ動き、結論として「現状維持」、つまり「見て見ぬふり」を選択していたのである。子供が庭で使う水の量が増えるたびに、何食わぬ顔で回り続ける水道メーターの微細な動きが私の心の平穏をわずかに乱す。
「これが『豊かさ』との対価か」。
無邪気な笑顔を前に蛇口をひねる指先を止められるはずもなく、資本主義の重みを感じる日々だった。
そんな状況で発見された、この小型の井戸。恐る恐る蛇口に手をかけると、驚くほどスムーズに回り、次の瞬間、透明な水が流れ出してきた。ポンプは、おそらく前の住人が比較的新しいものに交換していたのだろう。正常に稼働しているようだった。
「……これで、勝てる」。
私の心に、確かな勝利の予感が芽生えた。これで水道代に心をざわめかせることなく、子供に思う存分水を使わせてやれる。私の理想の古民家暮らしが、ようやく現実になる。一瞬、そう思った。しかし、現実主義者である私のもう一人の自分が、冷静にささやきかける。
「そんなお水で大丈夫か?」と。
古民家の井戸水、その実力を問う「水質検査」という名の審判
流れ出る水をガラスのコップに汲んでみた。見た目は特に濁っているわけでもなく、異臭もしない。私一人が庭の草木に水をやる程度なら、このまま使ってしまっても問題はないのかもしれない。
しかし、この水に触れるのは、私だけではない。子供たちが、この水で手を洗い、顔を洗い、あるいは夏の暑い日には頭からかぶることだってあるだろう。風呂の水だって大人の真似事のようにごくごく飲んでは「ぷはー」と大声上げるわが子だ。飲まないわけがない。
万が一があってはならない。理想の暮らしとは、何よりもまず安全の上に成り立つべきだ。私は、この未知の水に対して、科学的な審判を下すことを決意した。すなわち、「井戸水検査」である。
早速、井戸水の検査方法について調査を開始した。選択肢はいくつかあるようだ。専門の業者が現地に来て採水から検査まで行うプラン。あるいは、自治体や地域の保健所が受け付けている検査。そして、インターネットで購入できる検査キットを使い、検体を郵送する方法。
私が住む市でも受付を行っていることが判明した。さらに調べていくと、飲食店や事業者が営業許可のために行うような、約50項目に及ぶ詳細な検査というものも存在するらしい。その内容と信頼性は非常に高いようだが、費用を聞いて内心震えながらも、費用でビビってんじゃないかと思われるのもしゃくなので、さもまあ今回は値段だけ聞きたかったんですよ風を装って「あーそうなんですね。ありがとうございます」と私は静かに赤いボタンを押す。
約15万円。井戸一つのために、そこまでの投資はできない。それは、家庭菜園にプロの料理人を雇うようなものだ。私の目的は、あくまで家庭での利用における安全性の確認である。
冷静に、そして現実的に選択肢を比較検討する必要があった。我が家の用途は、飲用を主目的とするわけではないが、子供の肌に触れる可能性は十分にある。この状況における費用対効果の最大化。それが私のミッションだ。
選択と決断のプロセス、そして市役所へ
最終的に私が選択したのは、市が受け付けている11項目の定期検査に、細菌検査を追加するプランだった。これならば、大腸菌の有無といった衛生上の最低限の指標は確認できる。そして何より、費用は1万以下。これならば、現実的な「安全への投資」と言えるだろう。
受付窓口は二つあった。一つは市の施設で、もう一つは委託された検査センターだ。市の施設は受付時間が平日のしかも午前中しか受け付け不可でしかも2週間に一回という限られた時間のみ。対して検査センターは基本平日はいつでも対応しているらしい。利便性を考えれば後者だが、念のため電話で問い合わせてみることにした。
受話器の向こうから聞こえてきたのは、およそ公共サービスとは思えない、無愛想な声だった。私の質問に対する返答は、単語の羅列に近い。この短い対話から、私はコミュニケーションコストの増大を予測した。私は静かに礼を述べ、電話を切った。そして、心の中で検査センターという選択肢をそっとゴミ箱に入れて蹴とばしてパンチする。たとえ有限られた時間でも、気持ちよく手続きができる方が精神衛生上よろしい。
翌日、私は指定された容器に井戸水を汲み、受付時間内に市役所へと車を走らせた。窓口の担当者は非常に丁寧で、私の選択が正しかったことを確信した。手続きは滞りなく終了。検査結果は、1〜2週間後に郵送で届くという。
まとめ:新たな問いと共に、結果を待つ日々
古民家での暮らしとは、一つの問題を解決すると、まるでモグラ叩きのように新たな課題が地面から顔を出す、そういうものなのかもしれない。壊れたポンプという課題を回避した先に待っていたのは、「水質」という、より根源的な問いだった。
私は今、一通の封筒が届くのを待っている。その紙切れ一枚が、我が家の庭における水の価値を決定する。果たして、あの井戸は「聖なる泉」となるのか、それとも「ただの湿った穴」で終わるのか。それは、まだ誰にも分からない。
結果が届くまでの間、庭の掃除にでもこの水を使おうか、と一瞬考えた。だが、もし結果が「飲用不可」どころか「接触にも注意を要する」レベルの物質を含んでいたらどうしよう。そんな想像が頭をよぎり、私は結局、物置から水道のホースを引っ張り出していた。
水道代を節約するために見つけた井戸の、検査結果を待つ間、私は水道水を使っている。この一見すると矛盾した行為こそが、理想と現実の間で暮らす日常なのである。